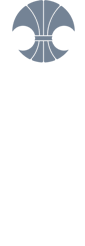2018年4月27日
In
Art
By
nakamura
シンガポールの建築デザイン事務所のMinistry of Desginと共創したDOTDOYの藍染めverです。
日本の手染めの素晴らしさを伝えるデザインのDOTDOT。コンセプトはプロセスの可視化です。今回の藍染めは両面に糊をおく非常に技術の難易度が高い技法で挑戦しました。両面に糊をおくのでその加減は非常に繊細で片面毎で止まる(浸透しない)様にするには糊の配合やヘラの力加減など多くの技術を必要とします。今回は、更にその両面糊おきを2回行い4層の色の濃淡を表現しました。微妙に色が変わるDOTは奥行きのある表情となりました。
...
2018年4月24日
In
Art
By
nakamura
中むらが参画しているシンガポールデザイナーとの共同プロジェクトの2年目の展示会を香港で開催しました。
2年目の取組は初年度に製作したDOTDOTの別技法を製作し、染色の多様性を伝えようというものです。技法は初年度の和更紗に引き続き、藍染め・引き染めにて製作をしました。また、生地の風合いも綿ピッケという薄手の生地にすることで光が透過した際の美しさを訴求しました。こちらは、摺りで片面を染める和更紗と違い、2年目の藍染めの浸染と引き染めは染色が裏まで浸透するからです。各々個性がある作品に仕上がり、これらをきっかけに日本の染色を提案したいと思います。
...
2018年4月23日
In
職人のわざ
By
nakamura
中むらのものづくりのリソースを納めたイメージビデオです。
中むらと暖簾づくりの活動をともにする職人は個人のユニークな技術を持った染め職人・染織作家などから、職人の道具をつくる職人、中規模の染色工場まで多岐に渡っています。伝統と現代、どちらにもその良さがあり、それらの多様性を総合的に提案することが技術の新たな販路を創造することに繋がると考えています。また、それらの技術や素材の特性を知り、職人と同じ方向を向いてものづくりをするディレクターが必要であり、中むらはそのような存在になれることを目指して活動をしています。
https://vimeo.com/207729855...
2018年4月12日
In
職人のわざ
By
nakamura
中むらで扱う暖簾の染色技法、和更紗のご紹介です。
和更紗(わさらさ)とは、日本で更紗模様を染める為に発展した多色の模様染めです。手描きや木版などの更紗染めはアジアでも用いられていますが、型紙を用いて染めるのは日本独自の染色技術です。型紙で染める際は、生地の上に型をおいて、その上から摺り(すり)刷毛という鹿の毛の刷毛で摺って染める技法で、色ごとに複数枚の型紙を使って染めることが特徴です。何度も何度も刷毛で摺って色の濃度を調節していく中で生まれる色は淡く日本らしい美しさがあります。
...
2018年4月9日
In
Topics
By
nakamura
暖簾は1枚の布を隔てて内と外を分ける認識としての結界です。
布を隔てて向こう側が視認できたり、気配を感じることができたりと緩やかに仕切る認識としての結界です。西洋文化の壁とは違い全てを遮断せずに、風を受けて柔らかになびく様は、自然豊かな日本で育まれた調和を好み大切にする日本人の精神性が育んだ価値観により形成されたと考えています。
...
2018年4月8日
In
Topics, 未分類
By
nakamura
暖簾は店先や屋内を仕切る布の結界で、紋や屋号を染めて日本の商家が紡いだ歴史や名声を表す「顔」として現代まで用いられてきた日本独自の文化です。
暖簾の始まりは、弥生時代に住居のチリや日よけとして現在の形の原型が生まれたと考えられており、平安時代に寝殿造の塀障具へとも派生しました。鎌倉時代に禅が普及すると共に「暖簾」という名が定着し、室町時代には意匠を染め抜くことで民家や商家の目印として用いられはじめました。その後、江戸時代に入り一大商業地となった江戸で、他店との差別化を図るため一気に屋外広告へと進化し、暖簾が店の顔でありブランドという概念が生まれました。そこから現代まで、暖簾は形を変えず日本独自の価値観とともに続いてきました。歴史の中で様々な変容を経て繋がってきた暖簾は日本独自の文化です。
...
2018年3月4日
In
イベント
By
nakamura
東南アジアマーケットの可能性について登壇しました。
代表の中村新が渋谷ヒカリエで開催中のJAPAN BRAND FESTIVALにて、KYO projectを通じて感じた海外デザイナーとの共創についてや東南アジアマーケットの可能性についてお話をさせて頂きました。来週9日〜はKYO project2年目のアウトプットとして香港で展示会を開催しますので、お気にかけて頂けたら幸いです。また、JBFは明日最終日も魅力的なコンテンツが盛りだくさんですので、ぜひ奮ってご参加ください!
...
2017年12月14日
In
Production
By
nakamura
SUS gallery コレド室町店の間仕切りを製作しました。
SUS galleryさんを運営するセブンセブンさんは新潟県燕市の金属加工会社で、とても色彩が鮮やかな「チタン製真空タンブラー」を製造するメーカーです。
今回の間仕切りは、そんなチタンのテクスチャーが光を反射する雰囲気を染めでも表現をしたいと考え、伝統的な引き染めという技法を用いてグレーと白とで縦にボカシて染めました。結果、空間とも非常にマッチする美しい間仕切りとなりました。
...
2017年9月20日
In
Work
By
nakamura
香川県高松市にオープンしたホステルSUNNY DAYの暖簾を製作しました。
数多くの魅力的な不動産を手がける、ひだまり不動産さまよりご依頼を頂きました。
施設のグレーでストイックなエントランスに暖簾の藍色がはいることでとても引き締まった印象となり美しい調和を生み出しました。中むらオリジナルの綿麻生地も良い具合に中の光を透過しており良いアクセントとなっています。また、屋内には麻生地の生成りの暖簾を誂え、優しく屋内空間を仕切ります。
...
2017年7月5日
In
Furniture
By
nakamura
ポマト・プロさまのオフィスのパーティションとして暖簾を製作しました。
オフィス内のミーティングに使用したり、書庫としての機能をもつオープンスペースを暖簾で緩やかに仕切っています。また、カラーは大胆にもコーポレートカラーである赤をふんだんに使い、エレベーターから降りると暖簾が目の前に飛び込んでくるインパクトを表現した遊び心のある暖簾です。
...