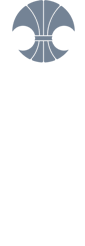2018年4月10日
In
Topics
By
nakamura
暖簾は江戸の文化です。
現在の屋外広告物という有形の価値と、商家の顔や資産であるという無形の価値は、江戸時代に江戸の問屋街での競争の中から定着しました。中でも、現在の「三井」の前身である「三井越後屋呉服店」が暖簾を広告物として画期的に活用しながら事業を大きく拡大して行きました。この頃には暖簾が屋外広告物として様々に使われ、現在の様式に定着しました。つまり、暖簾は江戸で育まれて進化・普及した江戸独自の文化といえます。西洋の紋章と違い、日本の家紋は庶民も持っているものでした。円を基調に様々な意匠の紋を染め抜いた暖簾が連なる景色は洗練された一体感のある日本らしい独自の景観です。
...
2018年4月9日
In
Topics
By
nakamura
暖簾は1枚の布を隔てて内と外を分ける認識としての結界です。
布を隔てて向こう側が視認できたり、気配を感じることができたりと緩やかに仕切る認識としての結界です。西洋文化の壁とは違い全てを遮断せずに、風を受けて柔らかになびく様は、自然豊かな日本で育まれた調和を好み大切にする日本人の精神性が育んだ価値観により形成されたと考えています。
...
2018年4月8日
In
Topics, 未分類
By
nakamura
暖簾は店先や屋内を仕切る布の結界で、紋や屋号を染めて日本の商家が紡いだ歴史や名声を表す「顔」として現代まで用いられてきた日本独自の文化です。
暖簾の始まりは、弥生時代に住居のチリや日よけとして現在の形の原型が生まれたと考えられており、平安時代に寝殿造の塀障具へとも派生しました。鎌倉時代に禅が普及すると共に「暖簾」という名が定着し、室町時代には意匠を染め抜くことで民家や商家の目印として用いられはじめました。その後、江戸時代に入り一大商業地となった江戸で、他店との差別化を図るため一気に屋外広告へと進化し、暖簾が店の顔でありブランドという概念が生まれました。そこから現代まで、暖簾は形を変えず日本独自の価値観とともに続いてきました。歴史の中で様々な変容を経て繋がってきた暖簾は日本独自の文化です。
...