2018年5月3日
In
Topics
のれん分けの変容(明治〜大正)
明治時代に入り商法大意が発令され、株仲間制度の廃止で商売が自由となり、その考えは大きく変わりました。
これは起業の機会ともなり、大商店は他業界への参入を可能にしました。また、従業員も主家と話し合いの末、支店という名目でののれん分けも可能となりました。当時の多くの従業員は、徴兵されない場合数年を主家で働き給料を貯めて独立しました。しかし、自己資金だけでは足りないので、主家の視点というのれん名をもらい、仕入業者にも主家の口添えのもとで商売を始めました。江戸時代との大きな変化は、支店が大きく普及したことでした。
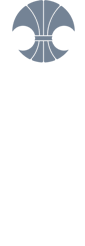


Sorry, the comment form is closed at this time.