2018年5月2日
In
Topics
暖簾分けとしての「のれん」の発祥(江戸時代)
のれん分けの発祥について
商家が永年商売を続け、築き上げた信用や知名度を営業上の市場の占有率などの無形財産を、屋号を印した暖簾に例えてのれん権といいます。商家では永年忠実に勤続した従業員を選び、のれん権の一部を分け与えて独立させることをのれん分けといい、のれん分けされた店舗は別家と言いました。江戸時代にのれん分けの制度が生まれたが、その当時は主家を絶対とした封建性が徹底されていました。江戸時代にのれん分けが生まれた背景は、当時の職業は家業が代々継承されて行き、その子々孫々の世襲を守るためと、株仲間という幕府公認の同業組合の仲間内で営業を独占することを守るためであると考えられています。
のれん分けを許されたものには、その商家の家紋とその物の名前が入った暖簾が与えられ、また本家から資本を得て独立して経営者となり新たな商売を始めるものは同業の商売、本家と同じ業者・得意先との取引が禁じられ厳しい制約がりました。また、その契約は子孫の代まで続くものであり、これは大商店になればなるほど厳しくなり、中小はもう少し情味があったとのことです。つまり、非常に親の力が強く、現代に比べて強制力の強い契約でした。
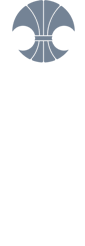


Sorry, the comment form is closed at this time.