
暖簾の色について
江戸時代では、暖簾の色は業種によって「ある程度」決まっていました。
色数の限られていた時代では、地色としては紺・藍・縹・柿・茶・浅葱などで、それに屋号などを白抜きしたのと、白地に墨で文字を入れたのが主でした。色の決め事に関しても商家が自店の伝統色を受け継いでいるなど実はそこまで決まった定式はなく曖昧なものでした。しかし、暖簾を広告媒体として用いる様になり自然発生的に色の大まかな定式ができたのは当時の風俗を想起させる面白さがあります。
a) 紺・藍:最も多く暖簾に使用される色であった。藍に虫除けの効果があるため、呉服商が用いたり、一般的な手堅い店がこの色を使っていた。
b) 縹(空色):派手な縹色は吉原の遊郭や引手茶屋の店先で使われていた。
c) 柿:柿渋で染めていたことから柿色と呼ばれていた。色味は歌舞伎の定式幕の茶色。遊郭で遊女の上品の太夫がいた店にだけ許された色とも言われており、太夫名を許された印として柿色の暖簾を与えられ、太夫のいる店は柿色、その他は空色・紺色が多かった。他にも一部の呉服店や料亭も柿色の暖簾であった。
d) 茶:赤みがかった茶の柿色に対し、黄味がかった茶色で主に煙草商が用いた。
e) 浅葱色:藍より淡い青。遊所で主に用いられていた。江戸の出会茶屋や大阪の盆屋や、芝居茶屋や相撲茶屋には浅葱色の地色の絵暖簾がかけらえていた。
f) 白:白地の暖簾は菓子商や薬商(当時は砂糖が薬であったため)が多かった。また、菓子店の中にはたれ毎に紺と交互に仕立てた暖簾も見られた。
g) 禁色:高貴な色である紫は一般には勝手に使えない色であった。また、色の印象が強い黄色や緑は暖簾には使われていなかった。
現代でも多様な色彩の暖簾がある中、その自由度に面白さがあると考えるので、あまり定式にこだわる必要はないと考えます。しかし、江戸時代の風俗を感じる上で知って置いても良いかと思います。


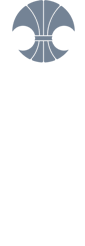


Sorry, the comment form is closed at this time.