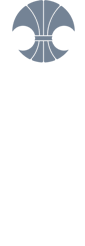のれん文化、アーケード文化
のれんは、日本人の誰もが知っているものですが、現代ではその意味性が失われつつあると感じます。のれんが日本人の暮らしから生まれ、日本の精神性が色濃く反映されたものだということを改めて発信していきたいのですが、のれんが進化・普及を遂げた江戸時代において、江戸の町や文化にはどのような時代性や精神性が息づいていたのでしょうか。
のれんは、江戸の風俗としてたくさんの資料が残っています。江戸の下町の景観をあらわした絵巻物や木版画には、必ずのれんが描かれるわけです。なぜかと言いますと、のれんには、白抜きの文字で屋号が描かれたり、お店の紋が染付けられていたので、江戸の町のどこかということの記号として初めて目にした人がすぐに自分をその場所に転移することができるという、ナビゲーションの役割を持っていたのではないかと考えられます。また、日本語の店という言葉は、“ 見せる” という意味に通じているわけですが、江戸の商習慣として、大きく2種類に分けることができます。1つは、店の前を通りかかった人たちが、店の前に出された品物を手にとって見るというスタイル。もう1つは、呉服屋さんが代表的ですが、店の中に入って、下駄を脱ぎ、畳の上で次々と奥から品物を出して見せる手法です。では、同時代の海外の街はどうであったか。
例えば、19 世紀のパリを描いた絵画やボードレールなど詩人、随筆家の文章を調べてみると、街の中には通路のようなアーケードが幾つもあって、1つひとつのアーケードに人の動線を引き込むような装置があったことがわかります。さらに一軒一軒の店内に飾り窓がつくられ、人はそれを見て中に入り、そこで割と自由に品物を見るというのが基本になっています。それに対して日本の通町ですとか、日本橋、京橋あたりの通りというのはずーっとのれんでつながっています。のれんは、外と内側の仕切りとしてソフトなバリアになっていて、お店の外に出しているものを見ることもできます。また夏になると朝顔の植木鉢をたくさん出したり、打ち水をしたり、お客さんを内側に誘い、迎え入れるためのビジュアル的に感覚を刺激する仕掛けが施されています。その中で、遠くから見てすぐにそこがどこのお店かわかるという役割をのれんが担っていました。このことは、江戸から明治、大正初期ぐらいまでの東京の街の大きな特徴です。その後、江戸の町に人災、天災が起こるわけです。
明治5年、京橋から新橋あたりにかけて大きな火事が起きました。この火事で、京橋以北は助かるけれども、銀座あたりはごっそりと焼けてしまい、それが銀座にレンガ街ができるきっかけになるんです。日本政府が焼けた土地をすべて買い上げて、そこに新しいレンガ造りの街をつくったのです。日本には存在しない、東アジアの地域でも上海の租界の他にはなかったある意味で人工的で、既存の文化とはまったく関係のない空間が、わずか3~4年という短期間に生まれました。周りは全部、江戸時代とほとんど変わらないまま、銀座だけがレンガ街として誕生し、都市の景観として非常に鮮やかな対称をなしていたのです。銀座の中央通りには、ヨーロッパのアーケードのような新古典主義的な列柱が連続し、ヨーロッパの地方都市ぐらいの街が江戸の中に突然できたわけです。その後、政府は民間に払い下げていったのですが、その時どんなことが起きたかと言いますと、当時の写真を見ると、みんな列柱のところにのれんをかけはじめるんですね。レンガ造りのビクトリア調の建物は、基本的にお客さんが扉を開けて中に入り、そこで商いが起こるわけですが、そのような商習慣は日本になかったので、お客さんが素通りしないようにのれんをかけたのです。これは世界史の中でもユニークな現象です。そういったところから明治時代の人たちが持っていた、のれんに対する身体感覚や商いへの期待値であるとかが見てとれる気がします。次に大正12 年、関東大震災が起き、銀座のレンガ街が完全に破壊されます。その後、アール・デコをはじめとしたモダニズムの建築、フラットで平坦な建築デザインが銀座の街にたくさん生まれました。ネオンも誕生し、ガラスの窓も作られ、のれんは表通りから姿を消していったのです。
なるほど、レンガ造りの建物にのれんとは、異質な組み合わせですが、おそらく当時の人たちには自然なことだったのかもしれませんね。他国の文化をうまく取り入れながら、自国の文化としてローカライズさせ、進化させてきた、日本人の精神性を反映していると私は思います。
精神性もそうですが、震災や天災が起きた時に、街をたちどころに再建可能なものにする木造密集地において、のれんというのは理にかなった調度の1つだったのだと思います。

守る、分ける、送る
西洋にも看板はありますが、日本ののれんのようにそれがメタファーとなってその店の技や権利を示すことはありません。のれんを守る、のれんを分けるなど、抽象的な概念として、のれんをとらえるという考え方はとても日本的です。紋や商標が染付けられているので、記号としてわかりやすかったのかもしれません。欧米において、店開きをする時に看板をあげたという話も聞かないですね。また日本では、相撲力士や俳優に対して、ファンの人がのれんを寄進することがありますが、贈ることで想いを届けるというような特別な意味が、のれんにはあるのかなと思ったりします。それも欧米では考えられないことです。
映画監督さんから俳優さんへの贈り物として、楽屋のれんを作らせていただいたことがあります。人と人とが思いを交信するために、のれんを使っていただけるのはとても嬉しいことですね。
僕は、20 代後半の頃、九州大学の専任講師として福岡に1年半ぐらい住んでいたことがあって、近所のみやこ食堂というお店にとてもお世話になりました。そこで、お礼にのれんをつくって差しあげたら、店先にかけてくれたんですね。それがすごく嬉しかったし、柿色の布に白抜きの文字でつくったのれんが博多の住宅地にすっと馴染んだような気がしました。私たちは、人にものを差し上げる時は、失せ物、つまり使って無くなるものがいいと教育されてきました。その点、のれんは消耗品ですし、俳優さんに贈る「楽屋のれん」などは期限付きで使われるものです。興行が終わったら、大切にとっておくことも、裁断して違うものにすることもできます。布でできたのれんを、お祝いであったり節目にあげるのはとても素敵なことじゃないかなと思うんです。

ヴァーチャルのれん
私たちは、ネット上の電子空間のピクセルでできている、物質ではないものにお金を払うことにだんだんと抵抗がなくなってきています。消費者経済学では、今後、さまざまな分野で脱物質化が進むと考えられています。レコードがDVD になり、DVD がデジタル配信になり、実体の物質が全くないものが消費されていく中で、洋服の世界でも電子区間だけにしか存在しないデジタルコレクションが販売されはじめています。例えば、中村さんが座っている写真を撮って、そのファッションブランドのサイトにアップすると、数日後に中村さんがそのブランドの洋服を着ている画像が届くしくみです。これまでもデジタルゲームの世界には、ヒーローの服装や武器をチェンジして楽しむものがありましたが、このファッションブランドはそれを真面目に真剣に作っていて、実体がないにもかかわらず、30ユーロとか結構いい値段で販売しているんですね。SNS上で自分のアイデンティティをファッションで表現したいと思ったとき、クローゼットの中にたくさん洋服を積みあげるぐらいなら、割り切ってSNSに投稿するために使うデジタルコレクションでいいのではないかという考え方です。
ブランドのコンセプトには、地球に足跡を残さない、フードロスのようにクロージングロスをなくすというような視点が書かれていますが、ヴァーチャルなコレクションというのはある意味ですごく理にかなっています。このような未来を考えていくとき、のれんというものが、ある意味でヴァーチャルな存在であるように私には感じられます。のれんは仕切りであったり結界であったり、いろんな意味合いを持っていますが、すっと通っていけるものでもあります。実体の物質として、お店を泥棒から守ったり、夜になると灯りがついて人を引き寄せることもない。のれんの役割は、人々の信頼とか期待値に依存していると思うんです。これから、3年後、5年後、A I やネット上にしか存在しないものがずっと私たちに身近なものになっていきます。その中で、のれんはヴァーチャルと実体の境に居続けられる気がします。ぜひヴァーチャルのれんを作って欲しいと思いますね。
なるほど…、確かにのれんの持つ「認識としての境界」という特性は、デジタルと結びつくかもしれませんね。海外のエンブレムと日本の紋章の図案をくらべたとき、エンブレムは写実的に情報を表しているのに対して、のれんは視覚情報をそぎ落として意味性を残しているというお話を紋章上繪師の方にお聞きしました。ヨーロッパは視覚を残し、日本は概念を残していると考えると、ヴァーチャルというのはじつは日本っぽい感覚かもしれませんね。
そうですね。でも、バーチャルになっていけばいいという話ではなく、実際に職人が作るということもとても大事です。のれんには強固な機能があるわけではないので、風に揺れているのれんというものがあってもなくてもいいかもしれませんけれど、なくなってしまうと裸な感じもします。のれんとは、プレゼンテーションやアイデンティティを明示するために不可欠なものという捉え方は、今後、電子空間に広がっていく物質をもたない、私たち一人ひとりのアイデンティティ、あるいは街のアイデンティティを形作るものを考える上でとても大事だと思っています。
ロバート キャンベル公式サイト https://robertcampbell.jp/
大正12年から平成17年まで着物のメンテナンス等を請負っていた家業の中むらを再稼働し、平成27年よりのれん事業を開始。日本の工芸や手工業の新たな価値づくりに挑戦しており、職人やクリエイターとともにのれんをつくるディレクターとして活動。のれん事業の傍らでつくり手の商品開発や販路設計にも取り組んでいる。
ロバートキャンベル 暖簾 のれん 製作 制作 中むら 中村新 東京 オーダーメイド