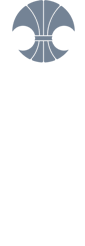“ 間” と“ 数寄”
私は松岡さんの提唱されている、漢語と和語の様に対照性を帯びたものが共存している“ デュアルスタンダードな日本” というお考えに感銘を受けました。そして、空間を遮断しないのれんは、その価値観を強く反映していると感じます。改めて、デュアルスタンダードという視点からのれんを掘り下げて頂けたらと思います。
どこから話しましょうか。根底にあるのは、日本の“ 間(ま) ” だと思います。のれんのみならず、表具、格子といった日本の調度はすべて“ 間”というものの上に成立しています。空間においても間仕切りであって壁にならない。出入り自由にしてある。そのあたりは、ヨーロッパの石の建築や、中国の土壁で四方を囲んだ四囲式の様式と大きく違います。常に出入りがデュアルであって、行ったり来たりできること。また“ 間” には単位があってそこから布一反の巾や、畳や障子の建具の寸法が決まったという意味では、“ 間” というのは日本の社会文化生活の単位を生んでいるものです。もう1つは、日本の家屋構造には、軒とか庇とか縁側があります。内であって外であって、内でなくて外でもない。例えば、他人の家の軒先でちょっと涼むとか雨宿りするとか、日本の家屋には内外を隔てないマージンという概念がずっとあったわけです。また湿気が高い国土であり、四季のうつろいが表情豊かであり、日本の空間は“ 間” を前提にして、風を通すとか、日が射すとか、人の声が聞こえるとか、あかりが漏れてくるとか、間接的鑑賞文化というものがありました。これらが、のれんとか障子とか、閉め切っているようでいて閉め切らない、閉じているようで開いている、開いているようでためらわせる、一歩そこに佇ませるというような、きわめて微妙な“ 間仕切り感覚” と言ってもいいようなものを成立させてきたんですね。さらに、日本にはシンボルとかアレゴリーというものの歴史が万葉の頃から続いていて、それがのれんに家紋や屋号を出すことにつながりました。こうやって考えてみると、“ 間” の文化、四季のうつろい、建具や調度の文化など、全部が見事に今なおのれんの中に成立していると思います。
そのようなお話をお聞きしていると、のれんを提案していくことの意義を改めて感じます。私はのれんにはもともとの意味合いを見つめ直すリバースエンジニアリングが必要だと考えています。
リバースエンジニアリングということで言えば、行ったり来たりする通過性というものを空間側がどこまで用意できて、のれんが主張できるかだと思います。のれんを擦過した瞬間に何かが起こるかだけではなくて、空間全体にその雰囲気を醸しだす必要があります。これは、大きく言うと、“ 数寄” ということだと思います。今、私が日本から世界に発信したいことが、この“ 数寄” の文化なんです。まさにのれんは“ 数寄” の構造の一端を担ってきたものです。スクリーニングというか、何かをすいて出てくるというのは髪を梳くとか、ペーパーを漉くとか、畑を鋤くとか、いろんなものを空気に混ぜて通りを良くして、ふっくらさせることであってそれが“ 数寄” なわけです。のれんの持っている“ 数寄” の力や“ 数寄” の美学というものをもっと提案してもらいたいですね。

絵付、キャンバス
ところで、のれんをつくるときの染めの技術は、これからも残っていけそうですか?
まさにそこが重要だと思います。私は、のれん文化を改めて提案をすることで、日本の染色の職人さんたちの新しい販路も設計したいと考えています。販路を捜している職人さんたちと、こだわりののれんをつくりたい方とのインターフェースとなり、職人さんたちの技術のコーディネートやディレクションを手がけています。三重県の温泉施設では美術家のミヤケマイさんの希望で現地の伝統工芸である伊勢型紙で型を彫り、呉服に用いる染色技法の和更紗で染めた巨大なのれんを制作しました。
マイさんはセンスが頭抜けてすばらしいと思います。彼女は「浮世」の「浮き」ということを完璧に理解をしていて絵にそれが活きています。世界に羽ばたいてほしいですね。マイさんの絵画をのれんに表現できるのであれば、それはキャンバスであり、絵としての第一歩だと言えます。江戸時代の中後期に蕪村や谷文晁( たにぶんちょう)や池大雅(いけのたいが) が布地に水墨画を描きたいということで、染屋か呉服屋が引き受けて、制作したものがいまだに残っています。
やはりピクチャライズするところをのれんが引き受けられるかどうかだと思いますね。
のれんがアーティストの方の表現の場になっていくのは、すごく素敵なことだと思いますし、挑戦していきたいですね。
今、のれんに使う素材は何が多いですか?
綿と麻が多いですね。
やはりデザインをどうするか、 素材をどうするかによって、のれんが普通のカーテンに段々と近づいたりするので、のれんののれんたる部分が必要になります。冒頭にもお話ししましたが、うつろいであったり、デュアルなものであることだったり、そこを和としてもう一度考えてみるということが大事です。

可能性を考える
松岡さんは、これまでにのれんをつくられたことはありますか?
丸の内の松丸本舗という書店の内装として長い水引のれんをかけたことがあります。またイベントなどでは、のれんを活用してきました。例えば、こののれんは、私の俳号である玄月の書をろうけつ染にしたものです( 前ページの写真) 。各界のクリエイターの方々をお招きして、宴を催すときに空間のあしらいとしてかけていたものです。また日本には幡( はた) というのぼりを垂らすものがあります。それから几帳、御簾。これのベント、つまり布の割れ方を研究されるといいと思います。ほとんどののれんは、ベントが合わさっているでしょう。それを肩で風を切って入るのもいいのですが、切れ目のところに結び目をつくってわざと少しだけ開けてつくっても面白いですね。それから裾の部分の長さが一致していなくてもよくて、たまに長さが違うものがあったりすると、ものすごく中に入って行きたくなる感じが出ると思いますよ。
考えることがまだまだたくさんありますね。私も日頃のれんで提供できるソリューションを考えており、例えば現代で増えているコミュニティスペースの広い空間をどう個人の空間に分けるかという課題にのれんが応用できると考え、試作開発に取り組みました。
コンパートメント化するということ?それも面白いですね。のれんだけで茶室ができますね。ポータビリティが高いし、海外でいいかもしれません。それから三段構えとか、五層とか、くぐってもくぐっても、のれん、のれん、のれんというのをどこかで作れると面白いですね。のれんをめくると次ののれんの模様が見えてくるみたいなことです。のれんでファサードやウインドウが隠れることによって、かえって次のVista というか光景を発見する喜びがあるわけですから、むしろウインドウの半分までのれんがかかっているぐらいがいいというような、それぐらいのことを提案されるといいと思いますね。
大正12年から平成17年まで着物のメンテナンス等を請負っていた家業の中むらを再稼働し、平成27年よりのれん事業を開始。日本の工芸や手工業の新たな価値づくりに挑戦しており、職人やクリエイターとともにのれんをつくるディレクターとして活動。のれん事業の傍らでつくり手の商品開発や販路設計にも取り組んでいる。
松岡正剛 暖簾 のれん 製作 制作 中むら 中村新 東京 オーダーメイド